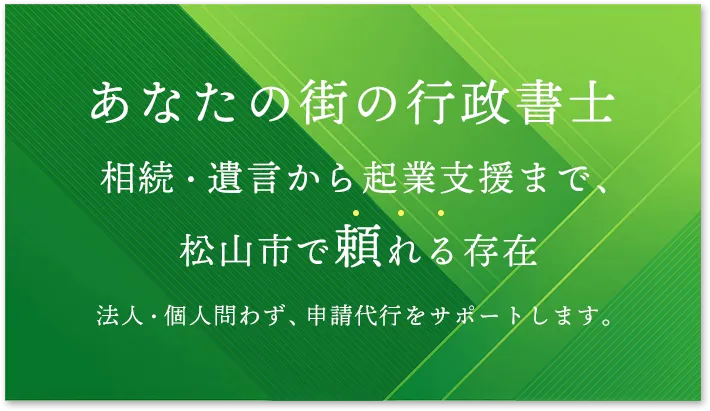令和の相続法改正(預貯金の仮払い制度)
2025/10/04
三つ目の改正は、“相続の仮払い制度(預貯金の仮払い制度)の創設”です。 相続の仮払い制度(預貯金の仮払い制度)とは、遺産分割が完了する前でも、法定相続人が一定額まで故人の預貯金を引き出せる制度です。 2019年7月の民法改正で導入され、葬儀費用や医療費など、急な支払いに対応するために設けられました。制度の対象となるのは法定相続人で、遺言による受遺者は対象外となります。 目的は葬儀費用、医療費、公共料金、家賃などの支払いで、例えば相続人の一人が葬儀費用を立て替えたが、他の相続人が協議に応じないとか、相続財産に借入金があり、返済期限が迫っているといったケースなどが考えられます。 必ずしも裁判所の許可は必要なく、仮払い制度には大きく分けて2つのルートがあって、それぞれ手続きの難易度や必要書類が異なります。 ①金融機関での直接手続き(裁判所の許可不要) もっとも一般的で簡便な方法で、裁判所の関与なしに、法定相続人が金融機関に直接申請できます。計算式は、預金残高×法定相続分×1/3で、金融機関ごとに上限150万円まで払い戻し可能で、仮払いされた金額は、後日の遺産分割協議で調整の対象になります。 また、一般的な必要書類は、被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)、相続人全員の戸籍・身分証明書・印鑑証明、金融機関所定の申請書などですが、金融機関によっては、相続人全員の同意書を求める場合もありますので事前に金融機関に問い合わせて確認されることをお勧めします。 ②家庭裁判所への仮処分申立て(裁判所の許可が必要) 金融機関での仮払いでは足りない、より高額な払い戻しが必要な場合や、相続人間で遺産分割協議が進まず調停・審判を申し立てている場合など、遺産分割前でも家庭裁判所が「必要性あり」と認めれば払い戻しが可能になります。 家庭裁判所への申立ての手続きとしては、まず、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てることが前提で、調停・審判の申立てと並行して預貯金仮分割の仮処分を申し立て、仮払いが合理的かつ必要と裁判所に認められる必要があります。 家庭裁判所では、仮処分申立てに関する相談窓口が設けられており、書式や添付書類の確認も可能ですが、裁判所ルートは時間と費用がかかるため、まずは金融機関での対応可能性を探るのが合理的ではないでしょうか。 制度の詳細については、事前に裁判所
----------------------------------------------------------------------
行政書士谷村日出男総合事務所
愛媛県松山市祝谷東町乙 768-24
電話番号:080-4030-5666
FAX番号:089-916-6120
松山市の相続手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------